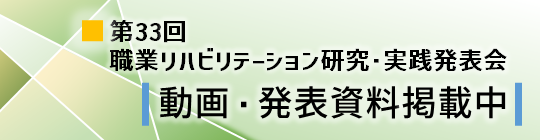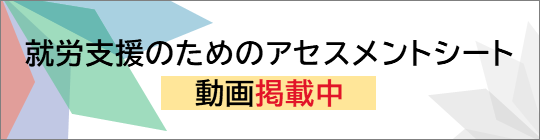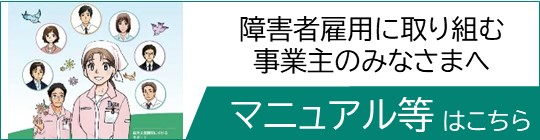調査研究報告書 No.71
軽度発達障害のある若者の学校から職業への移行支援の課題に関する研究
-
発行年月
2006年03月
-
職業リハビリテーション活動による課題領域の体系図・ICFによる課題領域の体系図 該当項目
執筆者(執筆順)
| 執筆者 | 執筆箇所 |
|---|---|
| 望月 葉子 (障害者職業総合センター主任研究員) | 概要、序章、第1章、第4章、参考 |
| 向後 礼子 (職業能力開発総合大学校福祉工学科講師) | 第3章、資料 |
目次
- 概要
- 序章 軽度発達障害のある若者の「学校から職業への移行」に関する検討課題 -本報告書の課題と発達障害の範囲-
- はじめに
- 1.教育場面での「指導上の困難」を「医療」の対象とする視点
- 2.なぜ「学校から職業への移行」を問題とするのか -「移行」という概念を必要とする背景-
- 第1節 職業リハビリテーションからみた「学校から職業への移行」の考え方 -発達障害のある若者が職業リハビリテーションを利用するタイミング-
- 1.職業的社会化の一般的な過程
- 2.発達障害のある若者の職業的社会化における特別な支援 -特殊教育諸学校からの移行-
- 3.発達障害のある若者の職業的社会化の課題 -通常教育諸学校からの移行と職業リハビリテーション利用のタイミング-
- 第2節 「学校から職業への移行」に関する研究を通して明らかにされた「発達障害」理解の問題点
- 1.通常教育に在籍する知的障害のある若者の「学校から職業への移行」の問題
- 2.「学習障害」を主訴とする若者の「学校から職業への移行」の問題 -事例研究が示唆すること-
- 3.「“軽度”発達障害」のとらえ方 -知的機能についての考え方-
- 第3節 本報告書の研究課題
- 1.通常教育に在籍した「発達障害」のある若者の就職の問題 -就職が障害理解の問題を避けて通ることができない場面となる場合-
- 2.「軽度発達障害」の周辺性について -NEET(Not in Employment, Education or Training)ではなくMEET'H(Marginal in Employment, Education or Training with handicap)として-
- 3.本報告書の課題と構成
- 【文献】
- はじめに
- 第1章 「学校から職業への移行」に何が起こっているか -本書の対象者をとりまく課題を俯瞰する-
- 第1節 若者の「移行」をめぐる変化
- 1.わが国における移行の仕組みのこれまで
- 2.長期化する移行期の内実
- (1)移行期の状態としての「フリーター」と「無業者」
- (2)若年無業・周辺的フリーター問題の背景 -若年雇用の位置-
- 3.顕在化する移行の問題
- 第2節 学校を経由した移行の現状 -移行が困難な若者たちの状況-
- 1.学校経由の就職の確からしさと限界
- (1)親の会の調査結果から
- (2)高校・障害児学校卒業生の就職実態調査結果から
- (3)移行が困難な若者たちの状況
- 2.「職リハサービスを選択していない若者」にとって高等教育の大衆化が意味すること
- (1)限りない進学の選択可能性の先にあるもの
- (2)学歴と求人の対応の現状と課題
- 3.移行の適時をどのように考えるか
- 1.学校経由の就職の確からしさと限界
- 第3節 特別支援ニーズへの対応 -学校在学中の支援の現状-
- 1.公教育における教育改革 -特別ニーズへの対応-
- (1)文部科学省の調査結果から -調査結果に含まれる障害特性とその出現率-
- (2)特別支援教育対象生徒に想定される義務教育終了後の進路
- 2.民間における支援の現状 -「不登校」という公教育からの離脱を中心として-
- (1)オルタナティブな教育に関する調査結果から
- (2)フリースクール白書から
- (3)調査結果が示唆すること
- 3.義務教育修了後における特別支援教育の現状と課題
- (1)後期中等教育における支援の課題
- (2)高等教育における支援の現状
- 1.公教育における教育改革 -特別ニーズへの対応-
- 第4節 「職リハサービスを選択していない若者」の理解のために -職業リハビリテーションにおいて発達障害を理解する-
- 1.発達障害の理解のために -発達障害者支援法における発達障害-
- (1)障害理解をめぐって -知的障害との関係-
- (2)診断をめぐって -優先的に診断される特性-
- (3)予後について -一時障害への早期対応/二次障害への青年期における対応-
- (4)ニーズに寄り添う/ニーズの再検討を支える
- 2.学校から職業へ -進路希望と利用可能な支援との間で-
- (1)職業リハビリテーションの支援の利用
- (2)学校紹介の移行システムの利用 -新規学卒としての入職-
- (3)若者が利用できる移行支援の枠組み
- 1.発達障害の理解のために -発達障害者支援法における発達障害-
- 【文献】
- 第1節 若者の「移行」をめぐる変化
- 第2章 移行経路から見た移行支援の現状と課題 -選択される教育の場と移行経路をめぐる検討の到達点-
- 第1節 職業リハビリテーションを利用した(利用を検討した)事例の移行経路
- 1.移行の特徴
- 2.C型・D型移行を選択した事例が示唆すること
- 3.学校から職業への移行支援に求められること
- 第2節 学校における問題解決の試み -高校卒業後の進路が示唆すること-
- 1.事例が示す意向の態様
- 2.高校卒業後の進路先の概要
- 3.移行経路が示唆すること
- (1)卒業時の進路選択をめぐって
- (2)進路選択後の移行経路
- (3)移行類型からみた特徴
- 第3節 まとめ -学校進路指導の課題/職業リハビリテーションとの連携の可能性-
- 1.移行経路が示唆する学校進路指導の機能と課題
- 2.職業リハビリテーションの選択可能性を高める課題
- 【文献】
- 第1節 職業リハビリテーションを利用した(利用を検討した)事例の移行経路
- 第3章 職業評価からみた移行支援の現状と課題 -青年期における再評価-
- 第1節 特性理解のための評価と課題
- 1.雇用対策上の障害の適用可能性 -知的障害の有無を明確化する-
- (1)知能検査の実施
- (2)一般職業適性検査
- 2.作業遂行上の特性評価について -「学習障害」を主訴とする者の就労支援の課題に関する研究が示唆すること-
- (1)作業遂行の正確さと速度を評価する -「視知覚認知」と「視覚-運動の協応」の困難について-
- (2)作業態度を評価する -検査と観察による評価の課題-
- 3.対人関係に関する評価について
- (1)対人関係に関する評価が求められる背景
- (2)対人関係を円滑に維持する能力の評価
- 4.まとめ -青年期における再評価-
- 1.雇用対策上の障害の適用可能性 -知的障害の有無を明確化する-
- 第2節 青年期における特性評価と進路選択(その1) -知能検査と一般職業適性検査を実施した44事例の検討-
- 1.一般職業適性検査に基づく対象者の類型
- 2.知能検査並びに一般職業適性検査の結果と進路選択について
- (1)障害者雇用を選択:卒業時点で療育手帳を利用した就労をした7名
- (2)一般扱いの雇用を選択:卒業時点で職業リハビリテーションを利用しない就労をした7名
- (3)障害者雇用を選択:障害者職業能力開発施設を経由し、職業リハビリテーション(療育手帳所持)を利用して就労した9名
- (4)進学を選択:10名
- (5)福祉を選択:5名
- (6)その他(アルバイト・在宅)の進路先を選択:4名
- 第3節 青年期における特性評価と進路選択(その2) -特性評価を実施した116名の検討-
- 1.知能検査並びに一般職業適性検査(器具検査)による評価と進路先
- 2.フロスティッグ視知覚発達検査/ベンダー・ゲシュタルト・テスト
- (1)フロスティッグ視知覚発達検査の結果
- (2)フロスティッグ視知覚発達検査と知能検査並びに進路との関連について
- (3)ベンダー・ゲシュタルト・テストの結果
- (4)ベンダー・ゲシュタルト・テストと知能検査並びに進路との関連について
- (5)まとめ
- 3.音声並びに表情から他者の感情を識別する:F&T感情識別検査
- (1)F&T感情識別検査の結果
- (2)F&T感情識別検査と進路との関連について
- (3)まとめ
- 第4節 青年期における再評価の現状と課題
- 1.青年期における再評価の課題
- (1)軽度発達障害のある若者の職業リハビリテーションの利用可能性
- (2)軽度発達障害のある若者の特性と進路について
- 2.青年期の再評価を実施する時期をめぐる課題 -通常教育に在籍する職業リハビリテーション対象者:知能検査の結果から何を読みとるか-
- 1.青年期における再評価の課題
- 【文献】
- 第1節 特性理解のための評価と課題
- 第4章 結語
- 第1節 職業リハビリテーションからみた「学校から職業への移行」の問題 -移行経路をめぐる検討の到達点と今後の課題-
- 1.「軽度発達障害」の周辺性と対応 -NEET(Not in Employment, Education or Training)ではなくMEET'H(Marginal in Employment, Education or Training with handicap)として-
- (1)「職リハサービスを選択していない若者」の円滑移行のためのモデルとは何か -通常教育における円滑な移行支援のために-
- (2)「職リハサービスを選択していない若者」の移行支援の課題とは何か -職業評価に基づいた移行支援のために-
- 2.職業リハビリテーションの利用可能性を高める要件と現状
- (1)医療化を促進する要件
- (2)学校教育における対応の現状
- 1.「軽度発達障害」の周辺性と対応 -NEET(Not in Employment, Education or Training)ではなくMEET'H(Marginal in Employment, Education or Training with handicap)として-
- 第2節 青年期から成人期への移行について -青年期における発達障害支援の課題と展望-
- 1.長期化する移行期の問題
- 2.職業リハビリテーションにおいて軽度発達障害の若者を支援するために残された課題-
- 【文献】
- 第1節 職業リハビリテーションからみた「学校から職業への移行」の問題 -移行経路をめぐる検討の到達点と今後の課題-
- 参考:現代の若者の「移行」に何が起こっているのか
- 1.移行と移行期 -長期化する移行期が意味すること-
- (1)わが国における移行の仕組みのこれまで
- (2)移行期の意味
- (3)移行をめぐる学校教育システムの機能とその変化
- 2.長期化する移行期の内実
- (1)移行期の状態としての「フリーター」と「無業者」
- (2)若年無業・周辺的フリーター問題の背景 -若年雇用の位置-
- 3.顕在化する移行の問題 -直撃されるのは、どのような若者か-
- 【文献】
- 1.移行と移行期 -長期化する移行期が意味すること-
- 資料
- 1.発達障害者支援法
- 2.日常生活能力水準(厚生労働省調査における別記)
- 3.F&T感情識別検査について
ダウンロード
サマリー
- ダウンロード (PDF/105.24KB)
分割
- 概要(PDF/885.88KB)
- 序章(PDF/1.96MB)
- 第1章 第1節 若者の「移行」をめぐる変化(PDF/709.75KB)
- 第1章 第2節 「学校から職業への移行」に関する研究を通して明らかにされた「発達障害」理解の問題点(PDF/1.91MB)
- 第1章 第3節 特別支援ニーズへの対応 -学校在学中の支援の現状- (PDF/1.29MB)
- 第1章 第4節 「職リハサービスを選択していない若者」の理解のために -職業リハビリテーションにおいて発達障害を理解する-(PDF/1.57MB)
- 第2章 第1節 職業リハビリテーションを利用した(利用を検討した)事例の移行経路(PDF/1.73MB)
- 第2章 第2節 学校における問題解決の試み -高校卒業後の進路が示唆すること- (PDF/3.78MB)
- 第2章 第3節 まとめ -学校進路指導の課題/職業リハビリテーションとの連携の可能性-(PDF/932.19KB)
- 第3章 第1節 特性理解のための評価と課題(PDF/1.33MB)
- 第3章 第2節 青年期における特性評価と進路選択(その1) -知能検査と一般職業適性検査を実施した44事例の検討- (PDF/1.13MB)
- 第3章 第3節 青年期における特性評価と進路選択(その2) -特性評価を実施した116名の検討- (PDF/1.59MB)
- 第3章 第4節 青年期における再評価の現状と課題 (PDF/1.27MB)
- 第4章 結語(PDF/834.46KB)
- 参考(PDF/2.92MB)
- 資料(PDF/1.03MB)
冊子在庫
なし