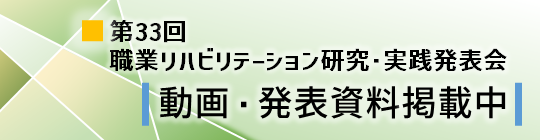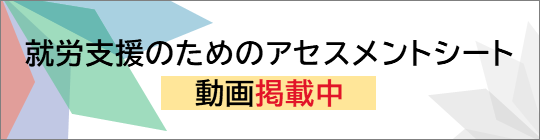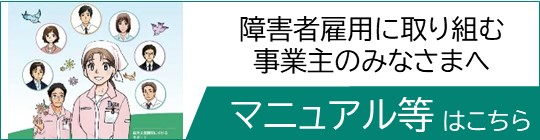効果的な就労支援に必要な知識・スキル等とその充足のための取組
2025年08月

1.はじめに
そこで、障害者職業総合センターでは、研修等の効果的な内容の検討に資することや、就労支援実務者と人材育成担当者が共通認識をもって専門性の向上に取り組むことができるよう、就労支援機関における多様な就労支援実務者が効果的な支援を実施するために必要な知識・スキル等の内容(これらの充足の取組も含む)を明らかにすることを目的とした調査研究を実施しました。そしてその結果を、「就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等に関する研究」(調査研究報告書No.180)としてとりまとめ、2025年3月に公表しました。
本稿では、調査研究の概要とその結果をもとに作成した巻末資料等について紹介します。
本稿では、調査研究の概要とその結果をもとに作成した巻末資料等について紹介します。
2.効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の言語化・体系化
上記のヒアリング調査やアンケート調査により得られた意見や結果を踏まえてリストの修正等を実施し、効果的な就労支援に必要な知識・スキル等については、16領域65項目と具体的内容を示す201の文と多岐にわたることを明らかにしました。なお、表1には16領域だけを示しますので、詳細は下記より調査研究報告書の巻末資料「効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の内容」(完全版は巻末資料4、要点版は巻末資料5)をダウンロードの上、ご覧ください。
| 1 | 障害者の就労支援の意義 | 9 | 就労支援のプランニング |
| 2 | 就労支援における支援者の基本的姿勢 | 10 | 職業生活に必要なスキル習得に向けた支援 |
| 3 | 障害者就労支援に関する法令・制度・サービス | 11 | 仕事の選択・求職活動や職場への移行の支援 |
| 4 | 企業経営と雇用管理 | 12 | 職場(実習中含む)への適応支援 |
| 5 | 様々な相手(障害者・事業主・関係機関・家族等)との相談・説明 | 13 | 職業生活を充実させるための体調管理や生活の支援 |
| 6 | 支援者間の記録・伝達 | 14 | 障害者雇用に取り組む企業のアセスメントと支援 |
| 7 | 障害者の自己理解・自己選択・自己決定の支援 | 15 | 関係機関や家族との連携 |
| 8 | 就労支援における障害者のアセスメント | 16 | 障害者雇用の啓発と支援人材の育成 |
- 巻末資料4「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の内容(完全版)」
(PDF/525.64KB)
- 巻末資料5「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の内容(要点版)」
(PDF/2.63MB)
3.人材育成における知識・スキル等の優先度や研修・OJT等のバランス
言語化・体系化された知識・スキル等について、人材育成における現実的な優先度の認識にばらつきがあることを踏まえながら専門性や支援力の向上を図るという観点から因子分析を行い、以下の4領域に分類しました。
- 障害者本人を中心とした多職種連携による職業生活の支援:基本的支援姿勢や個人情報の取扱い、人権、相手の立場やニーズを踏まえた説明、障害者本人のニーズを中心としたアセスメント、チームワーク、自己選択・自己決定支援、記録、計画とモニタリング 等
- 地域の企業や関係機関との関係構築と障害者雇用の周知・啓発:障害者雇用の啓発、企業経営や労働市場の動向把握、地域支援人材の育成、障害者雇用促進法等、地域の社会資源ネットワーク、障害者雇用状況の実態把握、労働関係法規や雇用管理の知識 等
- 職場適応・定着のための障害者本人と企業双方への支援:職務遂行と職場適応のための支援、職場見学や職場実習等、障害特性や雇用管理のポイントの説明、退職と再就職の支援、継続的フォローアップ体制構築、職場業務の調整、求人とのマッチング 等
- 障害者本人の自己理解と自信向上の支援:障害者の自己肯定感の回復支援、本人の自己探求の促進、専門的ツールの活用、職業との関わりでの自己理解支援 等
| 優先的とされていた習得方法 | 知識・スキル等の内容 |
|---|---|
| 研修中心 | 支援者が持つべき心構えと倫理意識 障害者差別の解消・禁止、虐待防止の理解と対応 障害者本人の自己肯定感の回復や自己選択・自己決定 障害者本人の強み・能力の把握 等 |
| OJT中心 | 支援者が取るべき態度 記録・伝達のスキル 求職活動や退職・再就職支援 職場・職務の調整支援 等 |
| 情報交換中心 | 関係機関との連携 企業情報の収集 生活支援 等 |
| 上記以外の組み合わせ (複合的な方法) |
相談の実施や支援計画の説明 事業主への支援 等 |
- 巻末資料7「就労支援実務者が効果的な就労支援を行うために必要な知識・スキル等の内容(4領域版)」
(PDF/523.65KB)
- 巻末資料8「研修や助言・援助などのニーズを検討できるチェックリスト(試案)」
(PDF/503.05KB)
4.人材育成に関する組織的取組の具体的内容
就労支援実務者が知識・スキルを習得するための人材育成の組織的取組とその効果を高める取組の具体的内容を表3のとおりに整理しました。
| 組織的取組 | 具体的内容 |
|---|---|
| 外部研修(外部機関が主催の研修)の受講効果を高める取組 | 研修の広報(案内のあった研修の情報を事業所内で回覧する等)、研修受講の目的の明確化、研修受講の意義の共有、研修受講中の業務への配慮、研修成果の活用 等 |
| 内部研修(所属する法人・機関のみで実施される研修)の受講効果を高める取組 | 所属スタッフによる研修の企画・立案、管理職が業務の中で意識的に研修の優先順位を上げる、オンライン・オンデマンド研修の活用、研修内容・成果の実践での活用 等 |
| OJTの効果を高める取組 | 体制の整備・指導方針の共有(マンツーマンでの指導やその方針の検討等)、組織内の心理的安全性の確立、初任者が主体的に学ぶきっかけの提供、面談を活用した悩みや不安の共有、記録等を活用したフィードバック 等 |
| 情報共有・事例検討の効果を高める取組 | 日常的な情報の共有、定期的な情報共有の時間の確保、負担の少ない(事前準備が少ない等)事例検討会の準備 等 |
| 支援者が持つべき心構え・倫理意識・態度 | 就労支援における障害者のアセスメント | 事業主との連携 | 地域の支援ネットワークづくり | |
|---|---|---|---|---|
| 初任者(おおよそ3年目まで) | ●外部研修や内部研修による基本部分の習得 | ●初回面接への同席・実施 ●他事業所への見学とその資料による学習 ●事業所内でのアセスメント会議への参加 等による基本部分の習得 |
●企業訪問への同行 ●OJTや研修を通して企業も支援対象であることを理解 ●面談会への参加 |
●地域ネットワーク会議への同行 |
| 中堅(おおよそ5年目まで) | ●初任者へのOJT | ●主担当としての面接の実施 ●アセスメント会議の運営・ファシリテーション |
●主担当としての企業見学・訪問 ●職場定着支援の実施 |
●地域のネットワークへの積極的参加 ●地域ネットワーク活動の提案 |
| 中堅 以上 |
●内外部での講師としての指導 | ●初任者の面接への同席・OJT | ●企業評価の実施 ●企業支援の実施 ●ジョブコーチ資格の取得 |
●行政機関等への就労支援に関する情報発信 ●地域ネットワークの運営 |
- 巻末資料9「こんなことでお困りではありませんか?~人材育成のポイントと留意点~」
(PDF/951.50KB)
5.まとめ
- 「効果的な就労支援に必要な知識・スキル等の内容」(巻末資料4、5、7):各領域の知識・スキル等についての習得状況の確認
- 「研修や助言・援助などのニーズを検討できるチェックリスト」(巻末資料8):各知識・スキル等について学習・習得する方法の確認
- 「こんなことでお困りではありませんか?~人材育成のポイントと留意点~」(巻末資料9):人材育成担当者が組織作りや指導体制を構築するための参考
本稿の元となる調査研究報告書No.180「就労支援実務者の専門性と支援力に資する知識・スキル等に関する研究」は、下記よりご覧いただけます。