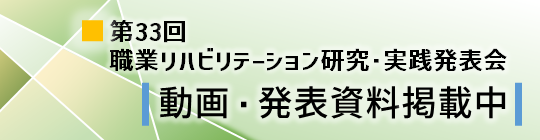第12分科会 職業評価・アセスメント
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 継続的な就労に課題のある就労移行支援事業所に通所する成人に対する刺激等価性/関係フレーム理論に基づく訓練の実施とその効果
【発表者】
岩村 賢(株式会社スタートライン CBSヒューマンサポート研究所 研究員)
【発表概要】
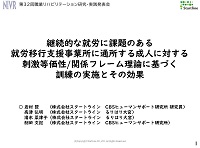
言語・認知能力に課題のある障害児・者に刺激等価性/関係フレーム理論に基づく訓練を実施すると、言語・認知能力の上昇や適応行動が改善することが明らかになっている。継続的な就労が難しく、就労移行支援事業所に通所する発達障害のある男性1人を対象に、刺激等価性/関係フレーム理論に基づく訓練を実施した結果、適応的な行動の増加が見受けられた。訓練の概要や訓練前後の量的及び質的な変化について報告する。
2 就労継続支援A型で「厚生労働省編一般職業適性検査」を用いて自己理解を深め、一般就労へ向けた支援の一事例
【発表者】
中島 実優(ヴィスト株式会社 ヴィストジョブズ金沢入江 職業指導員)
【発表概要】
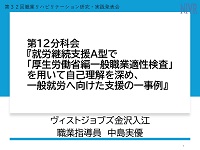
Aさんは双極性障害という診断を受けており、一般就労につきたいという思いはあるが、Aさんが自身の適性が分からないという思いから一般就労には至っていない。石川障害者職業センターで厚生労働省編一般職業適性検査を用いて検査を行い、その結果「手腕に適性がある」が「うっかりミスが多い」特性があることが分かった。それらを踏まえAさんが自身の適性を理解し、力を発揮できるよう一般就労に向けて実施した支援を報告する。
3 一般校からの就労相談にTTAP・BWAP2を活用したケース~アセスメントを通じての、家庭・関係機関との連携~
【発表者】
酒井 健一(社会福法人釧路のぞみ協会自立センター くしろジョブトレーニングセンターあらんじぇ 職業準備・職場定着係長)
【発表概要】

一般校からの就労相談は年々増加傾向にある。またそれに伴い、一般校でも障害者手帳を有している方については増加傾向であり、相談の件数も同様の状況がみられている。今回は一般校より相談のあった、障害者手帳を有している方についての進路等についてTTAP・BWAP2のアセスメントを行い、現在の本人のハードスキル・ソフトスキル等の整理を行い、その結果を共有することにより、進路選択の一助となったケースとなる。
4 MWS社内郵便物仕分(簡易版)による応用的アセスメント法の検討~健常者データの詳細な項目分析を通じて~
【発表者】
知名 青子(障害者職業総合センター 上席研究員)
【発表概要】
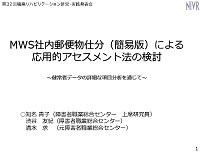
MWS新規3課題のうち「社内郵便物仕分」は活用率が最も高く(地域センターで75.3%、地域センター以外の機関で62.5%)、職業評価、職業準備支援、就労アセスメントの一環として利用されている。しかし同時に難易度の高さにより実施時間を要することなど利用上の難しさが指摘されていた。そこで本発表では、簡易版の有効性を高めることを目的に、健常者データを再分析し課題の項目特性について検討した結果を報告する。
5 「実行機能」の視点を用いた効果的なアセスメント及び支援に関する研究-実行機能に困難のある対象者の支援に関する調査から-
【発表者】
宮澤 史穂(障害者職業総合センター 上席研究員)
【発表概要】
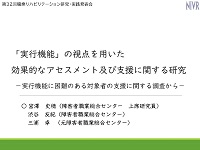
発達障害、精神障害、高次脳機能障害では職場において、仕事の手はずや段取りが悪い、時間内・期限内に仕事を終えられない、といった困難が生じている。本発表では、このような困難について、実行機能に注目し、全国の地域障害者職業センター等を対象に実施した、実行機能に困難が生じている対象者への支援に関するアンケート調査の結果について報告する。