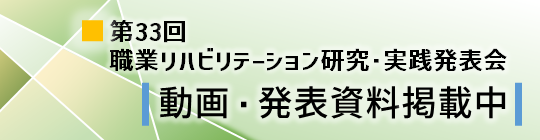テーマ11 精神障害
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
1 精神障害のある短時間労働者の雇用状況について(その1) ~特例措置適用企業を中心とした障害者雇用状況データの分析~
発表者
國東 菜美野(障害者職業総合センター 研究員)
発表概要
平成30(2018)年度より、精神障害のある人の雇用について特例措置(条件に該当する短時間労働者の雇用率のポイントを、従来の0.5から1とする措置)が適用されている。本発表は、厚生労働省の障害者雇用状況調査の分析結果から、特例措置が精神障害のある人の雇用に与える影響を検討するものである。なお、分析の対象は主に特例措置適用企業とし、雇用率達成状況や特例措置に該当する労働者の雇用状況等について考察する。
2 精神障害のある短時間労働者の雇用状況について(その2) ~事業所アンケートの結果を中心に~
発表者
渋谷 友紀(障害者職業総合センター 研究員)
発表概要
平成30(2018)年度より、精神障害のある人の雇用について特例措置(条件に該当する短時間労働者の雇用率のポイントを、従来の0.5から1とする措置)が適用されている。本発表では、平成30年度の障害者雇用状況報告の時点で特例措置対象者を雇用している事業所に対して実施したアンケート調査について、結果の概要を報告する。
3 精神障害のある短時間労働者の雇用状況について(その3) ~本人アンケートの結果を中心に~
発表者
小池 磨美(障害者職業総合センター 主任研究員)
発表概要
平成30(2018)年度より、精神障害のある人の雇用について特例措置(条件に該当する短時間労働者の雇用率のポイントを、従来の0.5から1とする措置)が適用されている。本発表では、平成30年度の障害者雇用状況報告の時点で特例措置対象者を雇用している事業所に就業している精神障害のある人に対して実施したアンケート調査について、結果の概要を報告する。
4 職業リハビリテーションにおける行動分析学の活用 -うつ病等を有する者へのACTを活用した実践事例-
発表者
佐藤 大作(秋田障害者職業センター 主任障害者職業カウンセラー)
発表概要
自己評価が低く、つらい過去の出来事や将来の不安などに悩み、就職活動を進めることが難しい一事例に対して、行動分析学等を基盤としたアクセプタンス&コミットメント・セラピー(ACT)を活用し、支援を行った。職業リハビリテーションにおけるACTの実施上のポイントや課題等について報告する。また、思考や感情といった私的出来事が含まれる問題との関わり方、支援方法等について行動分析学的な視点を踏まえて考察する。
5 就労支援のケース検討におけるPCAGIP法の適用について
発表者
早田 翔吾(ストレスケア東京上野駅前クリニック 臨床心理士・精神保健福祉士・公認心理師)
内田 博之(独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 中央障害者雇用情報センター 障害者雇用支援ネットワークコーディネーター)
発表概要
就労支援におけるケース検討の方法は様々あるが、方法によっては支援者を責める形になったり、うまく行かない部分を終始指摘する形になったりと、支援者の自信喪失につながる可能性をはらんでいる。本研究では就労支援における事例を、心理臨床場面で用いられるPCAGIP法と呼ばれるケース検討技法を使った検討例を示しながら、各就労支援の現場でも実践できるよう報告を行う。
6 K-STEPを使った精神障害者のセルフケア
発表者
下田 直樹(インクルード株式会社 ニューロワークス横浜センター サービス管理責任者)
発表概要
K-STEPとはセルフケアを実践しながら就労定着を図るためのプログラムで、毎日継続することにより可視化し、セルフケアの理解を進めることができる。就労移行支援に通う当事者のAさんは、スマートフォンにセルフケアシートを入れて毎日続けるうちに、自分の内面に起こる「ある内傾向」に気づき、気分変調のサインとそれに関わるトリガーとストレスコーピングの関係性をグラフにして見える化した。
- 発表論文
(PDF/932.32KB)
7 就労支援施設利用を促す中間的役割としての稲作ケアの可能性
発表者
鳥島 佳祐(医療法人常心会 川室記念病院 相談リハビリテーション部 作業療法士)
発表概要
当院では、高齢の認知症や精神疾患の患者を対象に集団作業を通して社会参加を促す稲作ケアプログラムを実施してきた。一方で、グループホーム利用の若年の精神疾患患者が本プログラムに参加し、就労施設利用に繋がった事例があった。地域が関わり、社会参加の機会を得て、集団内にて役割を担う中で、自信が回復し、就労意欲が高まったと考えられる。稲作ケアが就労施設利用を促す中間的役割としての機能をもつ可能性が示唆された。
- 発表論文
(PDF/1.27MB)