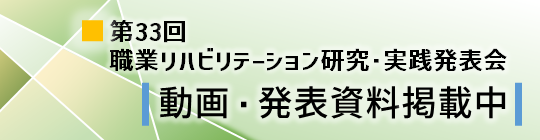第15分科会 高次脳機能障害
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 高次脳機能障害のある方の就労に向けて支援者が担う役割について考える ~支援者の立場から~
【発表者】
角井 由佳(特定非営利活動法人クロスジョブ クロスジョブ札幌 就労支援員(作業療法士))
【発表概要】
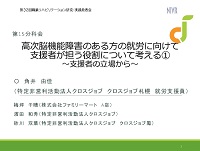
高次脳機能障害は見えない障害と言われている。高次脳機能障害のある方の就労は、本人だけではなく企業の理解と協力があることで成り立つことが言える。今回、高次脳機能障害のある方の新規就労を進める上で、企業との採用前からの密な連携を行ったことで就労定着が実現した事例を経験した。支援者の立場から、障害の見える化・企業の障害理解促進へ取り組んだことを事例を通して報告し、支援員が担う役割について考察した。
2 高次脳機能障害のある方の就労に向けて支援者が担う役割について考える ~企業の立場から~
【発表者】
梅坪 千晴(株式会社ファミリーマート A店 ファミマートレーナー)
【発表概要】
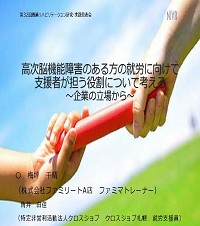
高次脳機能障害は見えない障害と言われている。高次脳機能障害のある方の就労は、本人だけではなく企業の理解と協力があることで成り立つことが言える。今回、高次脳機能障害のある方の新規就労を進める上で、企業との採用前からの密な連携を行ったことで就労定着が実現した事例を経験した。企業の立場から、障害の見える化・企業の障害理解促進へ取り組んだことを事例を通して報告し、企業が担う役割について考察した。
3 複合的な要因を抱え難渋した復職支援における就労継続支援B型の包括的な関わりについて ~家族支援と定着支援を含めた取り組み~
【発表者】
伊藤 裕希(NPO法人コロポックルさっぽろ クラブハウスコロポックル 支援コーディネーター)
【発表概要】
脳出血により右片麻痺、構音障害、高次脳機能障害が残存した40代男性。発症後約1年が経過した状態でかかりつけの医療機関からは高次脳機能障害を指摘されず、家族相談がきっかけでB型の通所利用となる。易怒性や易疲労性が強く、高次脳機能障害の拠点病院での検査を含め短期間でのサービス利用の為、他の就労支援機関との連携を図ることが難しい中で家族支援と復職支援を並行して行った実践と課題について報告する。
- 発表論文
(PDF/1.20MB)
4 就労希望のある亜急性期脳損傷患者データベースによる復帰群と外来移行群の比較
【発表者】
中村 滉平(浜松市リハビリテーション病院 リハビリテーション部 作業療法士)
【発表概要】

当院では作業療法士が主に脳損傷患者の就労支援を行っている。2021年より就労希望患者をデータベースに管理してきた。今回、亜急性期の入院病棟から退院後すぐに職場復帰した患者78名と外来移行し、就労に向けたリハビリテーションを継続した患者100名の差違を検証した。疾患や記憶検査の結果に優位差はなく、年齢と上肢麻痺の程度にのみ有意差を認めた。量的研究だけでは外来移行基準を明確に出来ない事が示唆された。
5 高次脳機能障害者の自己理解を進めるための支援技法の開発
【発表者】
狩野 眞(障害者職業総合センター職業センター 上席障害者職業カウンセラー)
【発表概要】
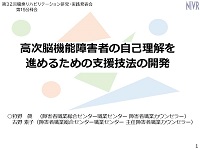
障害者職業総合センター職業センターでは、就職、復職および職場適応を目指す高次脳機能障害者への支援に役立つ技法の開発に取り組んでいる。本発表では、支援対象者自らが職務遂行上必要な補完手段を活用することや力を発揮できる環境を知ること、今後の働き方を考えること等、自己理解を促進するためのより効果的な支援方法を検討するとともに実際の試行状況について中間報告を行う。