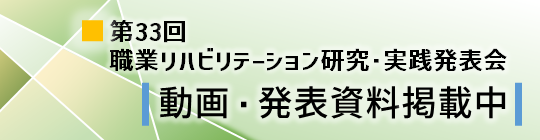第11分科会 福祉から一般雇用への移行Ⅱ
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 授産取引関係を通じた福祉的就労から雇用へのアプローチ
【発表者】
眞保 智子(法政大学 現代福祉学部 教授)
【発表概要】
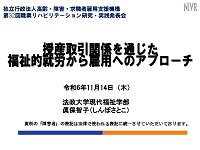
授産取引で構築した品質や支援力等の信頼をベースに、民間企業A社から就労継続支援B型事業所であるC事業所に発注されている製品の製造に習熟したC事業所の職員と利用者をA社が採用し、雇用が拡大する事例である。C事業所とA社は建物賃貸借契約を締結し、C事業所敷地内にA社の支社を設立している。課題は、A社の基幹的な社員が常駐せずに今後付加価値が高く、能力開発に資する商材を製造する職域拡大が可能かである。
2 多機能型事業所の就労への取組について
【発表者】
長峯 彰子(公益財団法人新宿区勤労者・仕事支援センター 福祉部 わーくす ここ・から サービス管理責任者)
【発表概要】
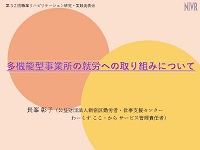
当事業所は、就労移行支援事業所、就労継続支援B型事業所、定着支援事業所と3つの機能を持つ多機能型事業所である。そして、就労移行支援事業所と就労継続支援B型事業所のそれぞれから就労者を輩出している。その細やかな支援と個別対応について成功事例を交えて発表していく。
3 企業と福祉の協働による知的障がい者の就業定着への挑戦~「キヤノンウィンドモデル」の実践を通して~
【発表者】
丹羽 信誠(社会福祉法人暁雲福祉会 「八風・be」 施設長)
【発表概要】
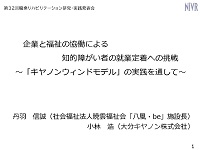
2008年に大分キヤノン株式会社と社会福祉法人暁雲福祉会は合弁に基づく特例子会社を設立。2009年に開催された第17回職業リハビリテーション研究発表会にて「福祉的就労から一般雇用への移行」をテーマとした分科会にて発表を行いました。それから早15年。知的障がいのある社員が安定して就業定着できるように「職域の拡大」や「合理的配慮」の実践を継続して取り組んできました。私たちの挑戦について発表します。
4 就労選択支援で職業訓練を選択する際のポイント~職リハにおけるSDM(Shared Decision Making)~
【発表者】
柳 恵太(国立職業リハビリテーションセンター 職業指導部職業評価課 障害者職業カウンセラー)
【発表概要】
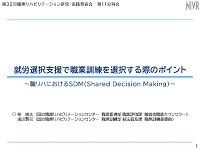
「就労選択支援」(就労アセスメント[障害者との協同による就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理]の手法を活用して、障害者の希望、就労能力や適性等に合った選択を支援するサービス)が令和7年10月から施行される予定であるが、就労選択支援を利用した際の選択肢に職業訓練も含まれている。本発表では、就労選択支援で職業訓練を選択する際のポイントについて報告し、選択の一助とする。
5 完全在宅就労移行支援による、在宅勤務就労事例
【発表者】
木村 志義(一般社団法人ペガサス 代表理事)
【発表概要】

在宅勤務を希望する障害者の方のための、フルリモート就労移行支援における、就労事例をお話します。