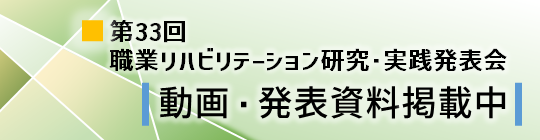第9分科会 企業における採用・定着の取組Ⅱ
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 社内支援技術向上を目的としたワーキンググループの取り組み
【発表者】
豊崎 美樹(株式会社スタートライン CBSヒューマンサポート研究所 主任研究員)
菊池 ゆう子(株式会社スタートライン CBSヒューマンサポート研究所 主任研究員)
【発表概要】
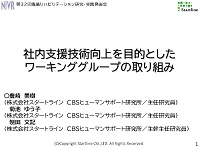
弊社は、障害者及び事業主の双方に対し、応用行動分析・文脈的行動科学に基づく専門的な知識・技術で職リハサポートを行っている。我々は、近年注目を集めているプロセスベースドセラピーを有効な理論として捉え、支援職が現場で活用できるよう、社内サポート職員を中心とした『PBTワーキンググループ』を設置した。当発表では、グループの活動と、メンバーによって収集されたPBT活用事例から得られた結果を発表する。
2 OCRデータ転記・PC入力課題による業務適性把握と業務配置転換への活用
【発表者】
志村 恵(日総ぴゅあ株式会社 人財戦略室 企業在籍型職場適応援助者)
【発表概要】
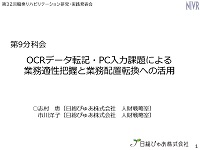
当社では、職場実習生(障害者)の職業能力を把握するためOCR(Optical Character Reader)データの文字(英数漢字・ひらがな・カタカナ)転記課題を取り入れている。昨年度(第31回)研究・実践発表会では、本課題が実習生の職能判定として活用できるという結果を報告した。今年度は当社の障害者社員に課題を実施し、業務適性の把握に活用する取り組みを行ったので、その結果について報告をする。
3 企業で働く障害者のウェルビーイング(Well-being)を高めるプランド・ハップンスタンス理論の実践
【発表者】
梅澤 馨(東急住宅リース株式会社 人事部勤労グループ マネージャー)
【発表概要】
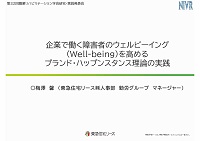
企業で働く障害者のウェルビーイングを高めるには、個々の好きなことや得意なことを伸ばす環境作りが重要です。心理的安全性の高い職場を提供し、障害に過度に配慮せず挑戦を促すことで成長を促します。人とのつながりをつくり、会社や社会に貢献することも欠かせません。プランドハップンスタンス理論を実践し、好奇心、持続性、柔軟性、楽観性、冒険心を育むことで、偶然を活かし、生産性向上や離職率低下の効果も期待されます。
4 「障害者雇用の取り組みから拡がるポジティブな意識変革」~当事者意識から生じたアクションに焦点をあてて~
【発表者】
木村 昌子(社会福祉法人聖テレジア会 本部事務局 主任)
【発表概要】

当法人は、障害児者・介護施設、回復期・急性期病院、在宅部門を有す。障害者雇用の行政措置対象の可能性をきっかけに、当事者意識が芽生え活動を開始した。アクションは、①人脈開拓・説明会、②情報共有・意思疎通、③会議活性化・発信、④雇用率可視化を実施した。成果は、1年で法定雇用率を達成し、採用活動の推進・人財は経営資源・仲間の尊重・職場づくりなどポジティブな意識変革が生じたので、その経過と課題を報告する。
5 障害者雇用の促進と社員満足度向上を図るカフェスペースの設置~超短時間労働の業務創出から始める本業のキャリアへの接続~
【発表者】
工藤 賢治(株式会社ゼネラルパートナーズ 事業サポートグループ シニアコンサルタント)
長尾 悟(株式会社JBSファシリティーズ ダイバーシティ・マネジメント事業部 部長)
【発表概要】
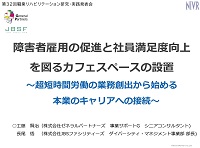
障害者雇用率2.7%を迎え、精神・発達障害者の雇用、社内理解、業務切り出し、職業準備性に不安がある方の採用、定着と課題が山積みなのが企業の現状です。従業員の福利厚生、ドリンクの受け渡しを通して障害者を知ってもらう、企業文化に慣れてもらう、就業することで自信をつけてもらう、双方にとって意味ある雇用に繋げるための企業内caféを始めました。福利厚生×ポジション創出×認知向上⇒価値ある障害者雇用を!