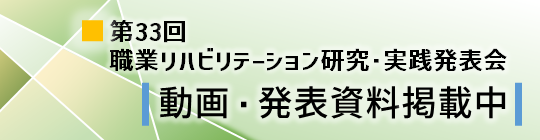第8分科会 難病/諸外国の取組
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 難病 ダイバーシティ研修の取組み~企業及び就労支援者への研修等による取組みによる考察~
【発表者】
中金 竜次(就労支援ネットワークONE 代表)
【発表概要】

増加する難病患者・難治性な長期慢性疾患患者への支援機関や企業の直面している昨今の状況に対応すべく、企業、支援関係者等への研修の取組みから得た参加者の感想、意見などもふまえ、難病ダイバーシティ研修の意義・及びその必要性を考察し、共有する。
2 慢性の痛み患者への就労支援の推進に資する研究
【発表者】
橘 とも子(国立保健医療科学院 保健医療情報政策研究センター 特任研究員)
丸谷 美紀(国立保健医療科学院 生涯健康研究部 特任研究官)
【発表概要】
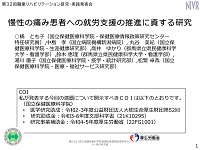
WHOのICD-11に追加された慢性疼痛(Chronic Pain)をもつ多様な人々の自己管理を、全人的に就労支援できる活力ある包摂社会体制の構築が目的。全人的な実態調査及び対策の方策を探り、症状に注目できるパーソナルヘルスレコード(PHR)活用調査方法及び慢性の痛みを持つ方の就労支援方法を作成した。成果は慢性疼痛の実態/就労支援対策だけでなく、未来投資戦略2017への貢献も期待できると考えた。
3 難病患者の就労困難性に関する調査研究(1)-患者調査(特に障害者手帳のない難病患者について)-
【発表者】
春名 由一郎(障害者職業総合センター 副統括研究員)
【発表概要】
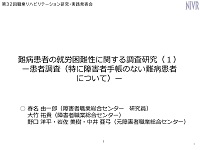
全国Web調査の回答によると、障害者手帳を申請していない難病患者3,410名の44%が身体・知的・精神の障害認定基準に含まれない「その他の心身機能の障害」等により、「かなり」以上の社会生活上の支障を経験し、特に、病状の進行の可能性や少しの無理での体調の崩れやすさ、体調の変動等は、職務遂行や業務調整等、職業準備や就職活動等の困難につながるが、職場や支援者等の理解や配慮が得られにくいものであった。
4 難病患者の就労困難性に関する調査研究(2)-事業所調査及び支援機関調査-
【発表者】
大竹 祐貴(障害者職業総合センター 上席研究員)
【発表概要】
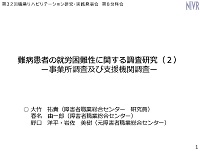
難病患者に対して現実的に実施可能な企業・職場の合理的配慮や地域専門支援のあり方を明確にするため、企業と支援機関へのアンケート調査を実施した。調査結果より、①難病患者に係る事業主への正しい理解の啓発や合理的配慮の提供の推進の課題、②難病患者の雇用のより一層の促進のための障害者雇用支援分野、産業保健分野、保健医療分野等の効果的な連携のあり方の課題が明確となった。
5 我が国と諸外国での障害者雇用施策の共通性と相違点を明確にする共通比較枠組みの試案
【発表者】
下條 今日子(障害者職業総合センター 上席研究員)
【発表概要】
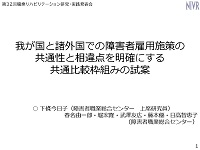
我が国の近年の政策課題(障害者手帳のない障害者等の就労困難性の捉え方、障害者雇用の質の捉え方、障害者雇用と福祉就労のあり方、医療・福祉・教育等の関係分野との連携強化や障害者就労支援人材の育成等)について、諸外国の近年の総合的な施策である、障害者の多様なニーズに対応するための支援体制の強化や、持続可能な雇用機会の創出等の取組みを比較しやすくするため、仮説的に12項目からなる共通比較枠組みを提案する。