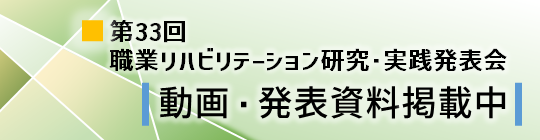第7分科会 精神障害
※ 発表資料を掲載していない方については、発表論文を参照してください。
※ タイトル及び概要は、発表者からいただいた内容を掲載しています。
また、共同研究者については省略しています。
1 精神障害者と働く上司・同僚の負担感の悪影響およびポジティブな意識変化に関する研究
【発表者】
金本 麻里(株式会社パーソル総合研究所 シンクタンク本部 研究員)
【発表概要】
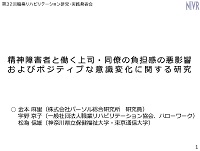
精神障害者の雇用では、業務のコントロールやコミュニケーション等に課題が生じることが少なくない。本研究から、これらの課題が精神障害者の配属現場の上司・同僚の負担感を増大させ、偏見の強化と支援行動の減少をもたらしていた。他方で、精神障害者を戦力化できる職場では、偏見の解消や多様性包摂の対応力・意識向上といった波及効果が確認された。本研究知見は、精神障害者の雇用の質向上に企業を動機づけるものと考える。
2 デイケアにおける就労という目標を通した自己肯定感のレジリエンスの事例紹介
【発表者】
泊 裕子(愛知県精神医療センター デイケア 精神保健福祉士)
【発表概要】
当院デイケアは長期利用者が多く、就労等を目指すことに自信がないという方が多くありました。そこで就労のための準備とした動機付けプログラムの実践を試みました。ようやく始めたところでコロナ禍という状況となり、見通しのできない社会情勢の中で、集まった参加者同士で励ましあいながら続けてきました。就労という目標を通して、障害により失いつつあった自己肯定感を回復させていく事例を紹介したいと思います。
- 発表論文
(PDF/1.28MB)
3 自然を利用したリハビリテーションによる職業準備性ピラミッドへの影響-事例マトリックスを用いて-
【発表者】
中塚 智裕(NPO法人えんしゅう生活支援net ワークセンター大きな木 作業療法士/生活支援員)
【発表概要】
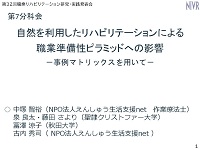
就労支援継続事業B型を新規利用する者は、気分変調により通所が不安定になりやすい現状がある。本研究の目的は自然を利用したリハビリテーション(以下「NBR」)を実施し、日常生活管理等の改善を探索した。対象は精神障害者で通所頻度が週3日以下の者とした。結果、対象者は通所頻度が改善し、また通所に対して前向きな発言が聞かれ、生活が安定した。NBRによって対象者自身の日常生活管理等を改善したことが示唆された。
4 複数の先行研究から考察される「障害者手帳を所持していない精神障害者・発達障害者の就労実態等」について
【発表者】
髙木 啓太(障害者職業総合センター 上席研究員)
【発表概要】

障害者職業総合センターでは2024年度から2025年度にかけ、精神障害又は発達障害を有して診断を受けているが障害者手帳を所持していない者に対する就労支援機関における効果的な支援方法や課題への対処等の検討に資することを目的に「障害者手帳を所持していない精神障害者、発達障害者の就労実態等に関する調査研究」を行っている。本発表は先行研究から把握した就労実態等について取りまとめた結果を報告し、考察する。